1.この本をおすすめしたい人
この本をおすすめしたいのは、以下のような方です。
- 言いたいことをうまく言葉にできない人
- 言いたいことや伝えたいことを言葉や文字にすることができるが、もっと表現力を伸ばしたい人
- プレゼンや会議でもっと分かりやすく、相手に刺さるように伝えられるようになりたい人
言葉にできる、というのは仕事や私生活において非常にメリットになります。
自分の気持ちや考えをうまく言葉にできていない、誰かと会話していてもちゃんと伝わっている気がしない、と感じている方に一読することをお勧めできる一冊です。
エッセンスだけ知りたい!という人は、ぜひ続きをご覧いただければと思います。
2.本書の概要
言語化に関する本が世の中にはたくさん出ていますが、伝達力(プレゼンなど)にフォーカスしたものが比較的多いと思います。
一方、本書では伝達力だけではなく、言語化(次の章で定義を紹介しています)の3つの要素について紹介しています。
言語化とは何か、言語化の3つの要素を知ることで、自分の言いたいことをうまく言葉にできていない原因を理解することができます。そしてどうすれば言語化力を高めていくことができるのも教えてくれるので、本書の内容を実践すれば言いたいことがうまく言えない、ということは格段に減っていくでしょう。
巻末には具体的なシチュエーションにおける言語化の実践見本もあるので、より自身の仕事や生活にあてはめて読むことが出来るので、テクニカル面でも深く知りたいという方の要望まで応えてくれています。
3.言語化力を高めた方が良い理由
そもそも言語化と何でしょうか?
本書では「頭の中にある考えや思い、情報などを的確に言葉にし相手にわかりやすく伝える力のこと。」と定義しています。
仮にこの言語化力が低いとどうなってしまうでしょうか?例えば…
- 周囲から評価されづらい
- 仕事が滞ってしまう(企画などが通りづらい、周囲の協力を得づらい 等)
- 会議などで落ち着かない(いきなり意見を求められてもうまく言葉にできない 等)
- 人間関係が円滑に進まない
このようなことが考えられます。
言語化力を高めることで、相手にわかりやすく、適切な表現で自分の意見や思いを伝えられるようになるので、仕事や私生活におけるコミュニケーションで悩むことは減るでしょう。
さらには、自分の意見を明確に示すことができれば、自分が何を考えているのかを相手にも理解してもらいやすくなので、互いの信頼感の醸成にもつながるでしょう。
4.本書の大事なエッセンス
すでにご紹介している通り、本書では言語化には3つの要素があると紹介されています。
そして、それぞれの要素をどのようにしたら伸ばしていくことができるのかについても紹介されていますので、本記事では特にポイントになる部分について触れさせていただきます。
1.語彙力
語彙力があるということは、使える言葉が多いということです。語彙力が高ければ、自分が言いたいことを的確に、表現豊かに伝えることが可能になります。
では、どのように語彙力を伸ばしていくのか?3つの方法があります。
①新しい言葉に「出会う」
普段自分が使わない言葉にであるためには、外から言葉のシャワーを受ける必要があります。
人にである場所に行き、会話を通じて新しい言葉に出会ったり、もしくは自分の表現が相手にうまく伝わっているかを反応を見ながら確認することもできます。
私が最も手っ取り早いと思ったのは、本を読むことです。ただ読むのではなく、「アクティブリーディング」というのをお勧めされています。私も一部実践していたこととして、「読んだ本の内容をアウトプットする」ということも含まれています。読むことで新しい言葉にも出会えますが、それを自分なりに言葉にしたり、文字にしてアウトプットすることで定着化を図ることができます。
②知らない言葉を「調べる」
①の新しい言葉に「出会う」の中で、知らない言葉に出会うことは少なくないはずです。
もし知らない言葉があれば、それがどのような意味で、どう活用される言葉なのかを調べることが大事です。
辞書でも調べられますし、最近はChatGPTに聞けば、ほぼ何でも教えてくれます。
調べる際には、「~とは?」と検索したり、類義語や対義語もセットで調べることで語彙力がさらに増していきます。
③脳に定着させて「覚える」
覚えるためには、アウトプットすることが重要です。①、②を通じて新しい言葉に出会ったり、知らない言葉を調べたとしても、その言葉を使わなければどんどん脳から抜けてしまいます。
インプットしてからアウトプットするまでの速度が重要です。本書では目安としてインプットしてから30分以内、また2週間に3回以上アウトプットすることを推奨しています。
また、覚えた語彙は「理解語彙」という知識として理解している言葉になりますが、それを「使用語彙」という普段から使っている言葉にしていくことで、自身の語彙力が上がったと初めて言えます。
「語彙力=言語活用能力」であるので、覚えた語彙を増やすのではなく、そこからさらに使える語彙を増やしていくことが重要となります。
2.具体化力
本書で一番の肝として紹介しているのが「具体化力」です。
具体化力とは、情報の解像度を上げることであり、つまり情報を整理することと言えます。
伝える情報が整理されていないと、いくら伝え方のテクニックを磨いたとしても、整理されていない情報を相手が受け取ることになるので、結果的に何も伝わらなくなってしまいます。
本書では、具体化するために以下の「ものさし」を紹介しています。
①メリット・デメリット
自分視点、会社視点など、いろいろな視点や立場から考えることができ、また多角的に考えることが可能になります。
②ビフォー・アフター
過去と未来、今と未来を比較することで、変化を生き生きと相手がイメージしやすく伝えることができます。
③類似点・相違点
似ているところと違うところを洗い出すことで、自分で気づいていなかったことを浮き彫りにすることができます。
例えば読書感想文を書くときに、物語の主人公と自分を比較することができ、読んだ感想を伝えるときや第三者について語りたいときにも有効的です。
④誰におすすめ?
ターゲットを明確にすることで、その人達が受け入れやすい内容(文章、価格、パッケージ、販促方法など)の詳細を詰めていくことができます。
⑤どうやって、どんなふうにして?
何かを行動に移す前の具体化にうってつけの問いです。手段や方法が見えてくると、ToDoに落とし込むことができ、行動に移しやすくなります。
まだ漠然としている場合は、「どうやって?」とさらに自問自答をしていくことで、さらに具体化していくことができます。
3.伝達力
言語化の最終ゴールは、相手に「伝わる」ことです。言葉をプレゼントと考えて、相手にただ渡すのではなく、喜んでもらうにすることが大事になってきます。
本書では話し方のコツについても紹介されていますが、ここではコツではなく、伝わるように話す5大原則について取り上げさせていただきます。
①相手に合わせて理解しやす言葉を使う。
聞き手の知識レベル(バックボーン)は様々です。中学生にも分かるレベルにするのが基本となりますが、ビジネスにおいては共通言語があるケースが多いので、あえて専門用語等を使って会話する方が話が分かる人だと聞き手に思ってもらうことができます。
②一文は60~70文字に収める。
一文につき、伝えたいことやメッセージは一つまでにしましょう。一文に複数もメッセージを入れると相手が理解しづらくなってしまいます。また複数のメッセージを一文に含めると、文章構造が複雑になり、ねじれ構造になってしまう恐れもあるため注意が必要です。
③アサーティブに伝える。
これは相手のことを尊重しながら、自分の意見や主張、感情を伝えることです。逆に相手に対する尊敬の念がなかったり、初めから反論する姿勢で会話をしてしまうと、建設的なコミュニケーションができません。建設的なコミュニケーションをするには、この姿勢は必須といえます。
④相手の反応を見る。
相手に「伝わっているか」を確認しましょう。もし伝わっていないようであれば、説明の仕方を変えたり、情報を補足する必要があります。
相手が「分かった」と言ったとしても次のようなサインがあるときは、伝わっていない可能性があります。サインを見逃さないようにしましょう。
例)表情が曇る、首を傾げる、眉間にシワが寄る、押し黙る、ぼーっとしてうわの空 等
⑤相手のニーズを把握する。
相手のニーズが分かれば、話そうとしている内容の中から不要な要素を除くことができ、相手に「喜ばれる」要約をすることが可能になります。
「2.具体化力」を実践することで、情報を豊富にすることができますが、その中から相手に必要な情報に厳選してみましょう。
5.まとめ
私自身、仕事や私生活の中でうまく言葉が出てこない、言いたいことはあるけどそれをどう表現したらよいか分からない、ということがよくありました。
本書を通じて、なぜ言葉がうまく出てこないのか、その原因と解決策の両方を知ることができました。
まだまだ上手く言語化できているとは言えませんが、本書の内容を実践することで少しずつ、言葉にしづらいということが減ってきたと感じています。
話が少し変わってしまいますが、本書の内容は語学学習にも活かせると感じました。
私は英語学習もしているのですが、「1.語彙力」=単語力、「3.伝達力」=スピーキング、ライティングとして意識できる部分だと思いました。
言語を問わず、言語化することは必要ですし、生きていくうえで必須のスキルでもあると改めて感じたので、今後も継続してブラッシュアップしていきたいと思います。
さらに詳しく本書の内容を知りたくなった方は、ぜひご一読ください!
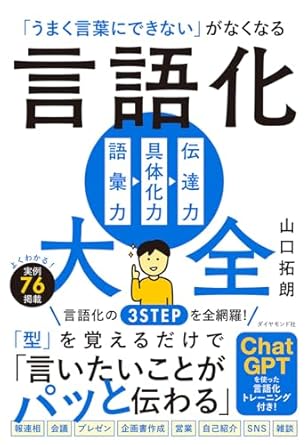
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/456c5183.65a5cf28.456c5184.0a9fa3f0/?me_id=1213310&item_id=21058350&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9266%2F9784478119266.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
